「人生経験したもん勝ち」がモットー。
習うより慣れよ精神で営業~バックオフィスの様々な業務を担当ののち、現在はマーケティング部門所属。
#お酒好き #千葉の山奥出身 #子育て奮闘中
イベントの成否は、会社の未来を左右することさえあります。新製品発表、周年記念、社内表彰、展示会出展…。そのひとつひとつが、社員や顧客、社会に向けた重要な「経営メッセージ」であり、経営戦略と連動した体験価値の設計が求められる時代です。同時に、参加者の感情や行動に直接影響を与えるイベントは、ブランドの信頼やエンゲージメントの向上にもつながります。だからこそ、“誰とつくるか”が結果を大きく左右します。
私たちワンコンシストは、イベントの力を最大限に引き出すことを使命と捉えています。単なる催し物の実施にとどまらず、経営層から現場までの一貫したメッセージ発信を支え、企業の持続的成長に寄与するイベントづくりを目指しています。
では、そのイベントを「どこに依頼すればいいのか?」という問いに対して、私たちワンコンシストのこれまでの実績や経験に基づいた視点でお応えします。私たちは、イベントの構成・企画構想から設計・運営・検証まで一気通貫で伴走するプロフェッショナル集団です。これまで培ったノウハウを活かし、大小問わずあらゆるイベントに対してカスタマイズされた解決策を提案します。イベントごとに異なる課題に真摯に向き合い、クライアントの経営戦略や文化に深く寄り添うことで、単発ではない持続可能な価値を生み出しています。
本記事では、イベント会社選びに迷うご担当者に向けて、失敗しないために押さえるべきことを軸に、私たちがどのような姿勢でお客様と向き合っているのか、大切にしている5つのポイントをご紹介します。イベントの目的設定から共創、失敗パターンの回避、戦略的予算設計、そして企業文化に根ざしたイベントづくりまで。これらのポイントを押さえることで、イベントは単なる催し物を超え、企業価値を高める重要な戦略ツールになるはずです。
目次
- 1 イベント会社選びで押さえるべきこと|失敗しないための総合チェックポイント
- 2 ワンコンシストが大切にしている5つのポイント
- 3 ポイント①|“イベントの目的”を起点にした設計だから、ブレない
- 4 ポイント②|「共創イベント」の仕組みで、企画から実行まで伴走
- 5 ポイント③|イベント“失敗あるある”を熟知しているからこそ、成功をつくれる
- 6 ポイント④|戦略的“予算設計”で、効果とコストの最適バランスを提案
- 7 ポイント⑤|“イベントづくり=企業文化づくり”という信念
- 8 まとめ|イベント企画会社選びの答えは「共創」と「戦略」にあり
イベント会社選びで押さえるべきこと|失敗しないための総合チェックポイント
①イベント会社のタイプ比較|自社に合う選び方とは
イベント会社にもさまざまなタイプがあります。まずは、自社の目的やイベント規模に応じて最適なパートナーを選ぶことが重要です。
例えば、単なる運営だけを任せたいのか、企画段階から伴走してほしいのか、特定のスタッフスキルを重視するのかによって、選ぶべき会社は変わります。
・企画専門会社:イベントの構想やアイデア出しに強く、ユニークなコンテンツ設計が得意です。特に、参加者に強い印象を残すクリエイティブな企画やブランド体験を重視するイベントに向いています。ただし、運営面のフォローが限定的な場合があるため、社内で準備や運営の担当者を確保しておく必要があります。
・運営一括型会社:設計から運営まで一気通貫で伴走するタイプです。準備段階の負担を減らし、当日の運営を確実に行いたい場合に適しています。また、スケジュール調整や関係者との連携も含めて任せられるため、安心して全体を任せたい場合におすすめです。
・人材派遣型会社:スタッフの手配や運営サポートを柔軟に補助する会社です。社内で企画を進めつつ、運営面だけ外部の力を借りたい場合に向いています。短期的な人手不足の補助や現場対応の強化など、必要な部分だけ外部リソースを使う場合に便利です。
自社に合う会社を選ぶポイント
イベントの目的:企画力が重要か、運営力が重要か
規模感・予算:大規模イベントは運営一括型、少人数イベントは人材派遣型など
社内リソース:企画や運営をどこまで自社で担えるか
経験・専門性:業界特化型や専門スタッフの有無
適切なタイプの会社を選ぶことで、イベントの成功確率を高めるだけでなく、社内の負担も大幅に軽減できます。自社の目的や条件に合わせて、最適なパートナーを見極めましょう。
②イベントの種類別|会社選びのポイント
イベントの種類によって、重視すべき会社の強みは変わります。単純に「実績が多い会社」だけでなく、自社のイベント特性に合った会社選びが成功の鍵です。以下を参考に、どのタイプの会社が適しているかを判断しましょう。
・展示会・商談会向け:商材の展示や来場者対応が重要なイベントでは、ブース設計や接客対応の実績がある会社を選ぶと安心です。経験豊富なスタッフが配置されているか、当日の運営体制やトラブル対応の柔軟さも確認しておくと、スムーズにイベントを進行できます。
・学会・セミナー専門:専門性の高いイベントでは、専門知識や語学力のあるスタッフがいるかが重要です。例えば、海外からの参加者が多い場合や、特定の学術分野に精通した司会・進行が必要な場合は、専門性に強い会社を選ぶことで、内容の正確性と参加者満足度を確保できます。
・地方/地域密着型:地方開催のイベントでは、交通・会場手配のコストや現地ネットワークの強さがポイントです。地元に強い会社は、会場選定や地元スタッフの手配がスムーズで、準備負担や予算の無駄を減らせます。
・オンライン・ハイブリッド型:オンラインやハイブリッド型のイベントでは、配信技術やシステム運用能力、参加者フォロー体制を確認しましょう。トラブル時のリカバリーや、参加者のサポート体制まで整っているかを事前にチェックすることが、スムーズな運営と参加者満足につながります。
イベントの目的や形式に合わせて会社を選ぶことが、成功率の向上と準備負担の軽減につながります。複数の候補会社を比較する際は、過去の実績・スタッフの専門性・運営体制を軸に検討すると判断しやすくなります。
③依頼前にやるべき「目的設計」の3ステップ
イベントを成功させるためには、依頼前に自社内で目的や体制を整理しておくことが非常に重要です。目的やリソースを明確にしておくことで、イベント会社とのやり取りもスムーズになり、成果につながるイベント設計が可能になります。
1. 目的・KPIの整理
まず、イベントで何を達成したいのかを言語化します。
・参加者数を増やしたい
・商談創出やリード獲得
・ブランド認知の向上
目的が明確であれば、会社選定や予算配分も判断しやすくなり、結果としてイベントの成果が可視化できます。
2. 内部リソースの整理
次に、社内で対応できる部分と外部に任せる部分を明確にします。
・「企画や設計は自社で進め、運営だけ委託する」
・「企画構想から運営まで丸ごと任せる」
この線引きを事前に整理しておくと、依頼時の認識ずれを防ぎ、効率的にプロジェクトを進められます。
3. タイムラインの明文化
最後に、準備から運営、撤収までのスケジュールを明文化します。具体的な期日や担当者を決めておくことで、社内外の関係者が進行状況を共有しやすくなり、当日の混乱やトラブルを防ぐことができます。
④失敗しないための事前質問リスト
イベント会社に依頼する際、契約前にしっかり確認しておくことで、トラブルや認識ずれを未然に防ぎ、安心してプロジェクトを進められます。以下のポイントを押さえて、事前に質問しておくことをおすすめします。
1.見積りに含まれる業務の詳細
見積りにどの業務が含まれているかを明確に確認しましょう。
- 会場設営や運営スタッフの手配
- 配信や音響・映像設備
- 事前準備や資料作成
詳細を把握しておくことで、追加費用や想定外の作業が発生するリスクを減らせます。
2. 緊急対応・トラブル対応の体制
イベント当日は予期せぬトラブルが起きることもあります。
- 当日スタッフの配置や連絡体制
- 機材トラブルやスケジュール変更への対応方法
事前に確認することで、トラブル時の対応力や安心感を把握できます。
3. 過去実績や顧客の声
会社の実績や他社事例を確認することで、自社のイベントに適した経験があるかを判断できます。可能であれば、同規模・同業界のイベント事例を聞き、参加者満足度や成果の確認も行いましょう。
4. キャンセル・延期時の対応ポリシー
予期せぬ事情でキャンセルや延期が必要になる場合もあります。
- 費用の取り扱い
- スケジュール変更の柔軟性
- 機材トラブルやスケジュール変更への対応方
あらかじめ確認しておくことで、契約後のリスクや不安を最小化できます。
事前質問を通して、会社の体制や実績、対応力を客観的に評価できます。特に見積り内容とトラブル対応体制は、費用対効果と安心感の両立に直結するため、慎重に確認することが重要です。
⑤契約後のフォロー体制も成功を左右する
イベントは、契約が成立した後もフォロー体制次第で成果の最大化が決まります。契約後の進行や確認体制が整っているかどうかを事前に把握しておくことが、円滑な運営と成果の可視化につながります。
1.ミーティングの頻度と内容
契約後の定例ミーティングの頻度や内容を確認しましょう。
- 週次・月次などの進捗確認
- 課題や懸念事項の共有
- 当日準備や役割分担の確認
適切な頻度での情報共有は、プロジェクトの遅延や認識ずれを防ぐ重要な手段です。
2. 進捗共有の方法や担当窓口の選定
担当者や窓口が明確かどうかを確認します。
- 連絡経路やツール(メール、チャット、管理システム)
- 担当者の責任範囲
担当窓口が不明確だと情報の取りこぼしや指示の遅延が発生しやすくなるため、進行管理の透明性を担保することが大切です。
3. 終了報告と振り返り
イベント終了後に、KPIレビューや参加者アンケートなどをもとに振り返りを行うか確認します。
- 達成度や改善点の共有
- 成果の可視化と次回への反映
終了報告があることで、イベントの学びを次回に活かせる“資産化”が可能になります。
4.次回提案や改善サポートの有無
契約後に、次回イベントへの提案や改善サポートがあるかも重要な確認ポイントです。継続的なサポートがあることで、イベントの品質向上や運営効率の改善につながります。
契約後のフォロー体制は、イベント成功の持続性や次回への改善に直結します。特に、進捗共有・振り返り・改善提案の有無を確認することで、単発のイベントで終わらず、継続的に成果を最大化できる体制かを見極められます。
ワンコンシストが大切にしている5つのポイント
ポイント①|“イベントの目的”を起点にした設計だから、ブレない
多くのイベントが失敗する理由は、「目的不在」で進行することにあります。
たとえば、「例年やっているから」「取引先に頼まれたから」という“なんとなく”の理由で動き出したイベントは、目的・効果・戦略が曖昧なまま進行し、最終的に成果が不明確な自己満足イベントになりがちです。
目的が不明確なままでは、会場構成やコンテンツ、演出の一つひとつに戦略的な一貫性が持てず、社内の合意形成や上層部への説得力ある報告資料の作成にも苦労することになります。また、参加者側にとっても印象に残らず、「何を感じて、どう行動すればいいのか」が伝わらないイベントになってしまいます。
私たちは、イベントの最初に必ず「そもそも、なぜやるのか?」「誰にどんな行動変容を起こしたいのか?」を言語化するフレームを提供します。
さらに、目的を明確にすることで、関係者間の認識共有がスムーズになり、プロジェクトの進行も円滑になります。これにより、イベントの効果測定や成果検証が可能になり、次につながる“資産となるイベント”へと進化します。
ポイント②|「共創イベント」の仕組みで、企画から実行まで伴走

イベントは、単なる“外注”ではなく、共に創るプロセスが重要です。
ワンコンシストでは、ヒアリング段階からお客様とチームを組み、イベントのビジョン・設計思想・構成を共に創り上げます。ここで重視するのが、社員や参加者の感情に働きかける“体験価値”の設計です。
特に重視しているのが、社員や参加者の感情に働きかける“体験価値”の設計です。たとえば、社内イベントでは「モチベーションの向上」「部門間の連携強化」「自社理念の浸透」などの行動変容につながるコンテンツ設計が求められます。
また、社外向けイベントであれば、「ブランドの世界観を五感で伝える」「顧客との関係性を深める」といった狙いを、空間・演出・コミュニケーションに落とし込みます。
私たちは、イベントを「短期的な盛り上がり」ではなく、「長期的成果へ導く仕組み」として構築します。
ポイント③|イベント“失敗あるある”を熟知しているからこそ、成功をつくれる
イベントのプロに依頼したはずが、こんな失敗が起きることがあります。
- 企画がふわっとしていて、参加者の印象に残らない
- 会場設計がバラバラで、導線が機能していない
- 現場でトラブルが起きても、リカバリーできない
- 成果の可視化がされず、上層部への報告が困難
これらはすべて、「経験不足」または「現場力の欠如」が大きな原因です。事前のプランニングが甘かったり、予期せぬトラブルへの備えがなかったりすることで、本来届けたかったメッセージや感動が参加者に届かず、企業としても貴重な投資の効果が見えにくくなってしまいます。
ワンコンシストは、イベント業界に20年以上従事し、年間500件以上のプロジェクトを支えてきた実績があります。
経験から蓄積した「失敗のパターン」と「成功の再現性」に基づき、準備段階で“つまずき”を先回りして対策する設計を行っています。
戦略なき予算消化ではなく、戦略ありきの予算設計こそが、イベント成功の鍵なのです。
ポイント④|戦略的“予算設計”で、効果とコストの最適バランスを提案
イベント企画において、悩ましいのが予算配分です。予算の使い方はイベントの成否を大きく左右します。
「どこにどれだけかけると、最大の効果が得られるのか?」「費用をかけたのに、本当に成果に結びつくのか?」という疑問をよく聞きます。
私たちは、イベントを**“目的達成のための戦略ツール”と捉える視点**で、以下のように設計します。
- 優先順位の明確化(例:演出よりも参加者動線)
- コストの変動要因の見える化
- ROI(費用対効果)を可視化した提案書作成
さらに、限られた予算内で最大限の効果を発揮するために、費用対効果を分析しながら柔軟に調整を行うことも重要です。
結果として、“なんとなく豪華にしたイベント”ではなく、“戦略的に意味のある投資”としてのイベントが実現します。
ポイント⑤|“イベントづくり=企業文化づくり”という信念

ワンコンシストが考えるイベントとは、単なる一日限りの催しではありません。
イベントは、企業が何を大切にしているか、どんな未来を描いているのかを社内外に伝える機会です。つまり、イベントは企業文化や組織ビジョンの可視化装置でもあります。
私たちは、イベントの中で表現される空間・言葉・演出・人の関係性すべてが、企業の本質的な魅力や課題を浮き彫りにする場だと考えています。単に楽しませるだけでなく、そこに企業の価値観や未来像をしっかりと反映させることこそが、本当の意味での成功だと信じています。
「社員が会社を誇りに思うきっかけをつくる」
「取引先との新しい関係を築く橋渡しをする」
「次世代リーダーが成長する舞台を提供する」
そんな意図を込めて、一社一社に合わせた“ビジョンあるイベント”を共に創り上げるのが、ワンコンシストのスタイルです。
企業の成長と文化の醸成に寄り添うパートナーとして、イベントづくりを通して未来を共に築いていきたいと考えています。
まとめ|イベント企画会社選びの答えは「共創」と「戦略」にあり
「イベント企画会社、どう選ぶべきか?」という悩みに対して、私たちは以下の視点を大切にしています。
それは、「目的」「設計」「体験価値」「共創」「行動変容」をキーワードに、経営戦略と連動する成果志向のイベントをつくることです。
ワンコンシストは、イベントを“感動体験”だけで終わらせません。
イベントを通じて、組織や顧客が行動を変え、企業が進化していく未来を共に描きます。
イベントづくりは、会社づくり。企業の理念や文化を体現し、社員や関係者の心を動かす重要な機会です。
私たちと一緒に、「意味あるイベントの仕組み」を構築しませんか?
私たちは、企画構想から運営、検証まで、一気通貫で伴走いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

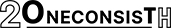
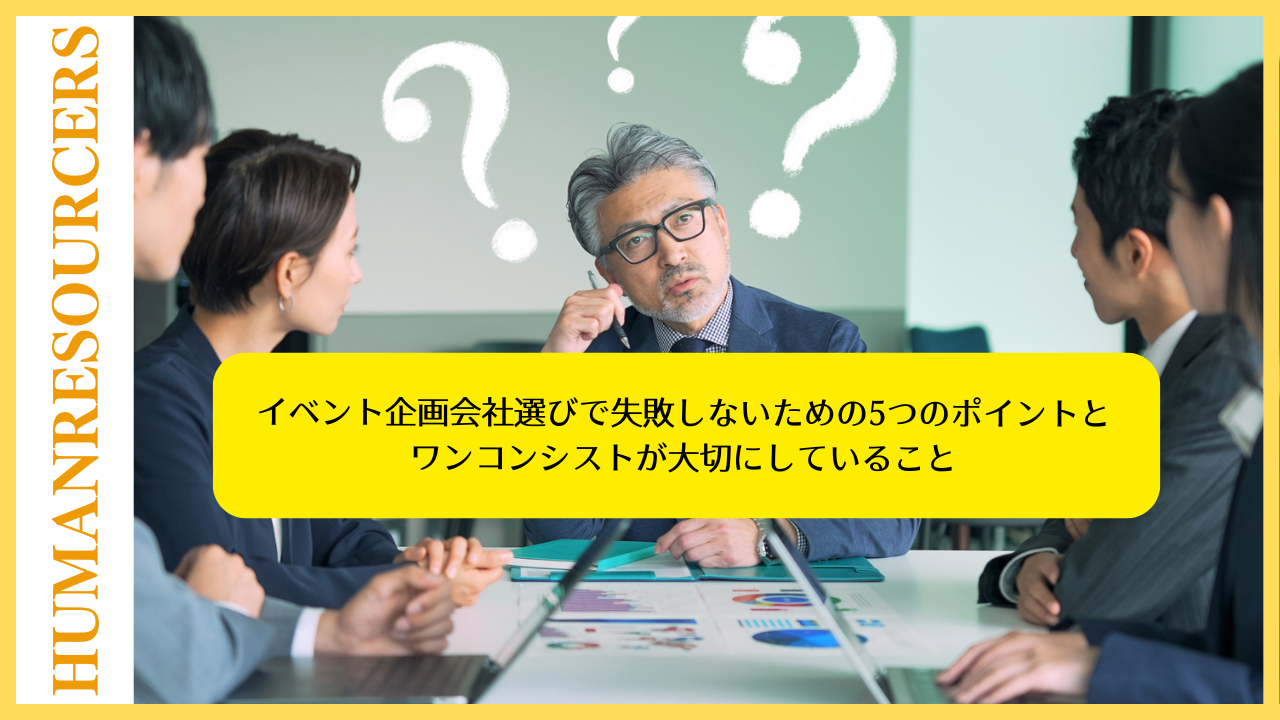
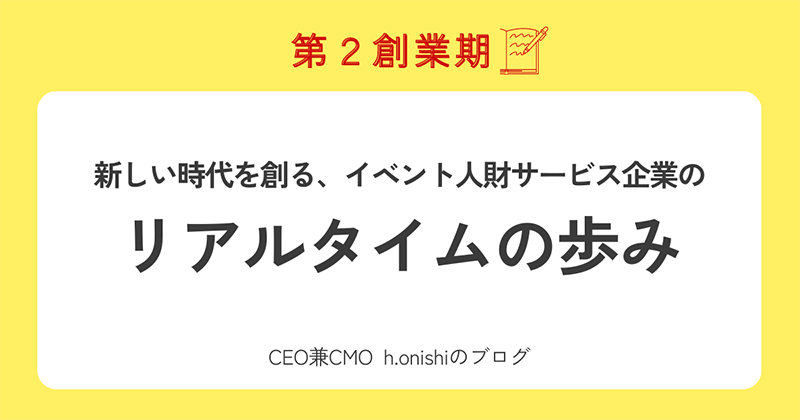

 TOP
TOP