(株)ワンコンシスト
CEO(最高経営責任者)兼CMO(最高マーケティング責任者)
2022年10月中旬、フラッと現れ勝手に経営改革を始め現在に至る。
こんにちは。ピロ大西です。
♯836です
1,000話まで残り164
2,000話まで残り1,164
経営者の「ヤバい」と
社員の「え、そうなんですか?」は
ズレている?
いつだったかなぁ
ある会議で出た”今期見通し”の数字を見て
僕は心の中で思った
「このままだと、◯月には現預金が底をつく」
すると
あるメンバーがこう返してくれた
「やばいですね
でも、◯月ってまだ◯ヶ月ありますから
なんとかなりますよ」
……この”なんとかなる感”で
どうやって資金繰りをするのか…
彼が悪いわけじゃない
むしろ前向きさには助けられている
ただ
「危機感は伝えても、伝わらない」
という残酷な現実…笑
さて本題です
経営者って
数字の「先」に怯える生き物だと思うんです
常にヒヤヒヤする状態で生きているので
その感覚は麻痺しているのかもしれませんが…笑
売上が落ち始めたら
翌月の粗利を計算して
半年後のキャッシュフローをシミュレーションし
「このペースだと3ヶ月後には…」
と未来から逆算する
つまり
“今すぐ何かを打たなきゃ”
という焦りに突き動かされている
一方で
社員の多くは
「昨日の現場どうだったか」
「来週の納品、間に合うか」
と、”今ここ”に一生懸命に生きている
これは至って当たり前のこと
だから
たとえば…万が一
「このままじゃ来期は賞与が出せない」
と経営者がヒヤヒヤしながら伝えても…
ガッカリはするかもしれないが
「え、そうなんですか?」と言い
翌日の動きが劇的に変わるかというと
そうでもない
このズレには
原因がいくつかあると考えています
ひとつは「情報の量と質」の違い
経営者は
“粗利率”と”固定費”と”人時生産性”の
交差点に大体立っているが
現場のメンバーが触れているのは
“目の前のToDoリスト”
もうひとつは「視点」の違い
経営者は
“会社全体の構造”と”未来”を見ているが
社員は”チームと自分の役割”にフォーカスしている
だからこそ
危機感を「共有」しようと思ったら
ただ“説明する”だけでは無理であり
“翻訳”が必要な訳です
たとえば
「営業利益が3ヶ月連続で赤字」→
「このままだと年末の採用予算はゼロになるかもしれません」
…など
危機感を”実感”に変換しないと
伝わらない…というか
動かない…動けない…
ちなみに
危機感の伝え方にも”温度調整”が大事
焦りすぎると
「また社長がパニック起こしてる」
と思われる
煽らなさすぎると
「なんか平和な感じですね」
となる
僕がたどり着いた結論は
「3割だけ焦らせる」くらいがちょうどいい
つまり
「ヤバいよ
でも、チームで打てば打開できるレベルだよ」
という温度感で
日々
経営者の”未来の焦り”を
“今の行動”に翻訳し続けること
危機感を伝えるって
ほんとに難しい
でも
それを怠ると
本当に「手遅れ」になってしまう
だから経営者は
毎月の数字にヒヤヒヤしながら
社員の背中をそっと押す
そして
このヒヤヒヤ感をどれだけ経験するかが
ひとを最も成長させる事も知っているので
大きな自己成長を臨むひとには
そういう挑戦の場を与えたい
そんな風に思うようになる訳なんですよね
未来の皆さんが
今の皆さん自身に感謝するように…笑
本日のランダム過去記事紹介はお休みしますm(_ _)m
今日はここまで。
またすぐに。

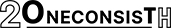
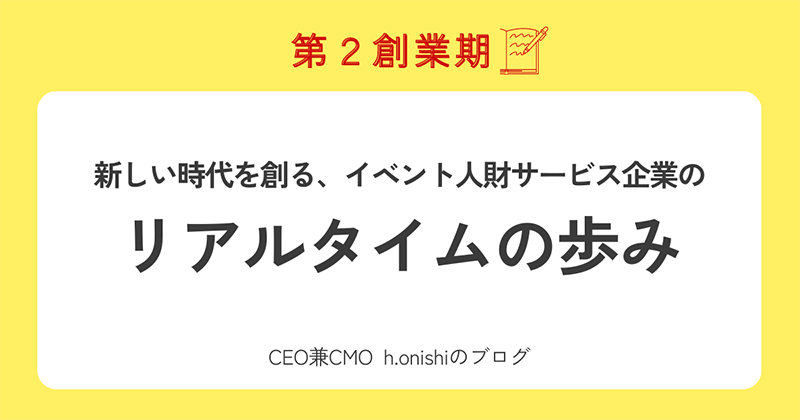
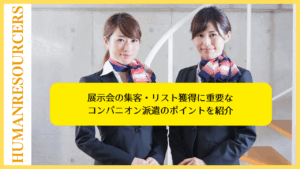

 TOP
TOP